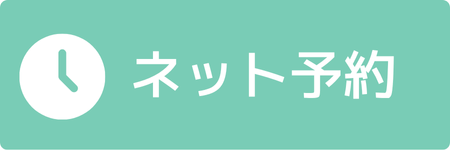インフルエンザ A型・B型の違い、症状、治療、予防接種の効果

毎年冬になると流行するインフルエンザ。特にA型とB型には症状や流行の仕方、治療法や予防接種の効果に違いがあり、患者さんから「A型、B型だと、どちらが重いのか」「治療薬は変わるのか」などといった質問をよくいただきます。
朝霞市・東武東上線「志木駅」の近くにある「志木新成メディカルクリニック」では、一般内科や呼吸器外来で、インフルエンザの疑いがある方の診療や、インフルエンザワクチンの予防接種などを行っています。
発熱や全身の痛みが強く出るA型、胃腸症状やだるさが長く続くこともあるB型。それぞれの特徴を理解することで、早期受診や家族への感染予防にもつながります。
この記事では、インフルエンザA型・B型の違い、症状、治療、家庭での対応、予防接種の効果までわかりやすく解説します。
志木新成メディカルクリニックは、朝霞市にあり、東武東上線「志木駅」から徒歩4分、駐車場も完備。
朝霞市・新座市・志木市などの近隣からだけでなく、電車でも車でも通いやすいクリニックです。
予防接種情報
志木新成メディカルクリニックでは、2025年(令和7年)10月1日から、インフルエンザ・コロナワクチン予防接種を開始しています。インフルエンザワクチン予防接種に関してはWEB予約もできます。
詳しくは「インフルエンザ・コロナワクチン予防接種を開始致します」でご確認ください。
インフルエンザとは
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって起こる急性呼吸器感染症で、毎年冬になると流行します。
38℃以上の高熱や関節痛、頭痛などの全身症状を伴い、通常の風邪とは異なる強い倦怠感や筋肉痛を引き起こします。特に高齢者、基礎疾患のある方、乳幼児は肺炎や脳症、心不全など重症化するリスクが高く、早期診断と治療が重要です。
A型とB型インフルエンザの違い
インフルエンザにはA型・B型・C型がありますが、主に流行するのはA型とB型です。
インフルエンザA型とB型の比較表
| 項目 | インフルエンザA型 | インフルエンザB型 |
|---|---|---|
| 主な感染対象(宿主) | 人・鳥・豚など幅広い動物に感染 | ほぼ人のみ(一部動物を除く) |
| 症状の特徴 | 高熱・強い悪寒・関節痛・筋肉痛・頭痛が急激に出る | 発熱は比較的緩やか、だるさや胃腸症状が続くことも多い |
| 潜伏期間 | 1〜4日(平均2日前後) | 1〜4日(ほぼ同じ) |
| 感染力・感染期間 | 発症前日〜発症後5〜7日程度感染力あり | A型と同程度 |
| 流行時期 | 毎年12月〜2月に流行のピーク | A型より遅く、2月〜4月にかけて増える |
| 流行規模 | 大規模な流行・パンデミックの原因となる | 流行は限定的だが毎年発生 |
| 重症化リスク | 高齢者・基礎疾患患者で肺炎・脳症など重症化しやすい | 小児では胃腸症状や脳症の報告あり、重症化も起こり得る |
| ワクチンの効果 | 発症予防・重症化予防に有効(H1N1・H3N2対応) | 発症予防・重症化予防に有効(山形系統は近年検出ほぼなし) |
| 合併症 | 肺炎、脳症、心筋炎、急性呼吸不全など | 肺炎、脳症、特に小児で胃腸炎症状が目立つことも |
インフルエンザA型とは
インフルエンザA型は、毎年の季節性流行の中心となりやすい型であり、ウイルスの変異が大きく、世界的な大流行(パンデミック)を引き起こす可能性がある型です。人だけでなく鳥や豚など多くの動物にも感染し、動物同士あるいは動物と人の間でウイルスの遺伝子が組み替わることによって、新型インフルエンザウイルスが生まれることがあります。症状は高熱、強い悪寒、関節痛、筋肉痛、頭痛などの全身症状が急激に現れやすく、肺炎・脳症・心筋炎など重症化リスクも比較的高い傾向にあります。
潜伏期間は1日〜4日程度で、症状が出る前日から発症後5〜7日程度まで他者に感染させる恐れがあります。日本での流行は例年、冬の初期(12月頃)から始まり、1〜2月に最も患者数が増える傾向があります。ワクチンによって発症や重症化を予防でき、A型にはH1N1・H3N2など複数の系統があるため、その年に流行が予測される型に応じたワクチン株が使用されます。
インフルエンザB型とは
インフルエンザB型は主に人に感染するウイルスで、A型と比べて変異の幅が小さく、世界的なパンデミックにはつながりにくい型です。近年まで「山形系統」「ビクトリア系統」の二つの系統が存在しましたが、山形系統は近年ほとんど報告されておらず、消滅の可能性も指摘されています。
症状はA型と同じく発熱や咳、倦怠感が現れますが、成人ではA型ほど急激な高熱と全身の痛みを示さないこともあり、微熱やだるさが続く程度で気づかれない場合もあります。小児では腹痛・下痢・吐き気などの胃腸症状を伴うことが多く、学級・家庭内で広がることがあります。
日本での流行のピークはA型より遅く、冬の後半から春先(2月〜4月)にかけて増えやすい傾向があります。ワクチンはA型と同様に重症化予防に有効で、特に基礎疾患がある人や高齢者、小児では接種が推奨されます。
インフルエンザの種類による主な症状の違いと経過
どちらの型でも高熱、頭痛、関節痛、咳、鼻水、喉の痛みなどが現れます。
A型では急に高熱が出て、その数時間後から全身の震えや悪寒が生じることが多く、筋肉痛や関節痛のような身体の痛みが強く出る傾向があります。
B型では熱がやや低く、微熱程度で済む場合もあり、代わりに胃腸の不快感や倦怠感、食欲低下が長く続くケースがあります。乳幼児では熱性けいれん、基礎疾患のある方では肺炎や心筋炎などの合併症も起こりやすくなるため、経過を慎重に観察することが必要です。
インフルエンザの診断と治療
インフルエンザ治療では抗ウイルス薬が用いられ、体内でのウイルス増殖を抑えることで、症状の期間や重症化リスクを減らします。発症から48時間以内に治療を開始するほど効果が高くなります。
代表的な治療薬にはタミフル(オセルタミビル)、リレンザ、イナビル、ゾフルーザなどがあります。基本的にはA型・B型どちらにも効果がありますが、近年では一部のA型H1N1でゾフルーザへの耐性例が報告されています。一方でB型では、タミフルやイナビルの効果がやや遅く感じられるケースがありますが、臨床的には重症化予防という観点から投与が推奨されます。
基礎疾患のある方や免疫力が低下している方では、肺炎や脳症などの合併症を防ぐため、早期の服薬が特に重要です。呼吸器疾患を持つ患者さんや喘息の方では、吸入薬が使いにくいため、内服薬(タミフル)やシングル投与型のイナビルが選ばれることがあります。
インフルエンザ予防接種の効果とA型・B型への違い
インフルエンザワクチンは、感染を完全に防ぐものではありませんが、発症率を下げたり、感染した場合でも重症化や入院のリスクを大きく減らす効果があります。特に高齢者、糖尿病や心疾患・呼吸器疾患を持つ方、妊婦、小児では重症化リスクを下げる効果が明確であり、医学的にも接種が推奨されています。
従来使用されているワクチンは、A型2種類(H1N1・H3N2)とB型1〜2種類(ビクトリア系統・山形系統)を含む「4価ワクチン」でした。これは毎年世界中に報告されるウイルスの流行傾向を参考に、その年に流行しやすい株が選ばれています。B型の山形系統は最近ほとんど検出されていないことから、2025年は製薬会社側でも「3価ワクチン」の準備が主流となってきています。当院でも2025年は「3価ワクチン」を使用予定です。
A型は流行の中心となりやすくワクチン接種による感染予防効果も高いため、接種後約2週間で抗体が形成され、3〜5か月間効果が続きます。B型も同様に重症化を防ぐ効果がありますが、特に小児や学童期ではB型による胃腸症状や長引く発熱を軽減するという観点でも有用です。
予防接種情報
2025年(令和7年)10月1日から、インフルエンザ・コロナワクチン予防接種を開始しています。
詳しくは「インフルエンザ・コロナワクチン予防接種を開始致します」でご確認ください。
A型とB型での家庭内対応の違いと注意点
家庭での対応はA型・B型とも基本的には共通しており、安静・水分補給・解熱鎮痛薬の使用・周囲への感染拡大防止が中心になります。しかし、型によって注意すべき点に違いもあります。
A型では高熱と全身症状が強く出やすく、急激に体力を消耗するため、脱水や体の痛みによる倦怠感が強く出る傾向があります。体力の低下した高齢者や心肺疾患のある方では、肺炎・呼吸不全へ移行するリスクがあるため、咳や呼吸の苦しさが強い場合は早めに医療機関を受診することが必要です。
B型では症状が比較的緩やかに始まることが多いため、本人や家族が「ただの風邪」と判断して外出や登校を続けてしまい、結果的に家庭や学校で感染が広がる場合があります。特に小児では嘔吐・腹痛・下痢など胃腸症状が目立つため、脱水や食欲低下から体力を失うことがあるため注意が必要です。
家庭内では、発症者と同じタオルや食器を共有せず、こまめな換気、マスク着用、加湿を心がけてください。高齢者・乳幼児・妊娠中の方・持病のある方が同居している場合は、感染を防ぐために部屋を分けたり、看病者を限定することも大切です。
インフルエンザに関するよくある質問
高熱が典型的な症状ではありますが、発熱を伴わないインフルエンザも存在します。
特に高齢者や免疫力が低下している方では、発熱が目立たず、倦怠感や咳、食欲不振だけで経過するケースもあります。また、発症して間もない時期では熱が上がる前に体のだるさや悪寒だけが出ることもあります。家族や職場で流行が見られる場合や、急に体がだるくなった、関節や筋肉が痛いと感じた場合は、熱がなくてもインフルエンザを否定できません。
強い症状が出ていない状態で医療機関を受診してインフルエンザと診断されることには、いくつかの意味があります。すべての人に必要というものではなく、状況によって判断が変わります。
まず前提として、インフルエンザ検査は「症状が出てからすぐ(通常12〜48時間以内)」が最も正確であり、症状がほとんどない段階(熱がない、体がだるくない)では検査の精度が下がります。そのため、無症状の方や違和感だけの段階では、検査をしても陰性になり、感染そのものを捉えられない可能性があります。
しかし、次のような場合には、症状が軽くても検査や診断に意味があります。
・高齢者、乳幼児、妊娠中の方、喘息・COPD・心疾患・糖尿病などの持病を持つ方の場合は、早期診断によって重症化を防ぐために抗インフルエンザ薬を検討することができます。
・家族内や職場・学校でインフルエンザが流行しており、自分自身に関わる人への感染を避けたい場合には、診断を受けることで出勤・登校の判断や感染拡大防止の対応がとりやすくなります。
・受験や大事な仕事・入院・手術などを控えている場合には、インフルエンザかどうか事前に確かめることで安心材料となることがあります。
一方で、まったく症状がなく元気で過ごせている方が「念のためだけ」で受診する場合は、検査をしても診断が難しかったり、治療が不要だったりすることもあります。インフルエンザは「病名をつけること」よりも「他人にうつさないこと」「重症化させないこと」が大切ですので、不安な場合は医療機関に相談の上、受診の必要性を一緒に検討することをおすすめします。
予防接種を受けてから免疫がつくまでにはおよそ2週間ほどかかり、その後3〜5か月程度効果が続くとされています。日本では流行のピークが12月から3月頃に多いため、例年10月から11月に接種しておくと、免疫が最も必要な時期に効果を発揮します。ただし時間とともに抗体は少しずつ低下していくため、毎年接種することが重要です。当院でも10月から接種を開始しています。
予防接種情報
2025年(令和7年)10月1日から、インフルエンザ・コロナワクチン予防接種を開始しています。
詳しくは「インフルエンザ・コロナワクチン予防接種を開始致します」でご確認ください。
接種した部位の赤みや腫れ、軽い痛みが最も多く、通常は数日以内に自然に消えます。全身のだるさ、微熱、頭痛や関節の痛みが出ることもありますが、多くの場合軽度で、1〜2日で治まります。重い副反応はまれですが、じんましんや息苦しさ、アナフィラキシーなどが起こる可能性もあるため、接種後30分ほどは院内で様子を見ていただくことがあります。過去にワクチンで強いアレルギー反応を起こした方や、卵アレルギーがある方は事前に医師へ相談してください。
発症する1日前から、発症して5〜7日ほどは体外にウイルスを排出し、他の人へ感染させる可能性があります。発症初期の2〜3日間が最も感染力が強いとされます。小児や免疫力の低下している方では、ウイルスを排出する期間が10日ほど続くこともあります。解熱したからといってすぐに登校や出勤を再開すると、周囲に感染を広げることがあるため、学校保健安全法や医師の指示に従って再開時期を判断することが大切です。
強い息苦しさや呼吸困難、意識がもうろうとしている、けいれんが起こった、高熱が続き水分が取れない、尿が出なくなった、唇や顔色が青白いなどの症状がある場合は、肺炎やインフルエンザ脳症、脱水など重症化の可能性がありますので、ためらわず救急受診してください。
特に小児では、嘔吐を繰り返す、高熱が続いたあとに反応が乏しい、意味のない言動がある場合は脳症のサインのこともあるため、早めの受診が必要です。高齢者では咳が弱く痰が出せない、食事が摂れない状態が続くことも重症化の兆候となります。
まとめ
インフルエンザA型とB型は同じインフルエンザであっても症状や流行傾向に違いがあり、適切な理解と早期対応が重要です。呼吸器外来や総合内科では、迅速な診断に加え、症状や基礎疾患に応じた治療を行います。発熱や全身のだるさが強い場合、自己判断で出勤や登校を続けず、早めに医療機関にご相談ください。予防接種や日常の対策により、重症化や周囲への感染を防ぐことができます。
当院でもインフルエンザに関する相談や予防接種を随時受け付けていますので、心配な症状がある方はお気軽にご相談ください。
志木新成メディカルクリニックは、
朝霞市にあり、東武東上線「志木駅」から徒歩4分、駐車場も完備。
朝霞市・新座市・志木市などの近隣からだけでなく、電車でも車でも通いやすいクリニックです。